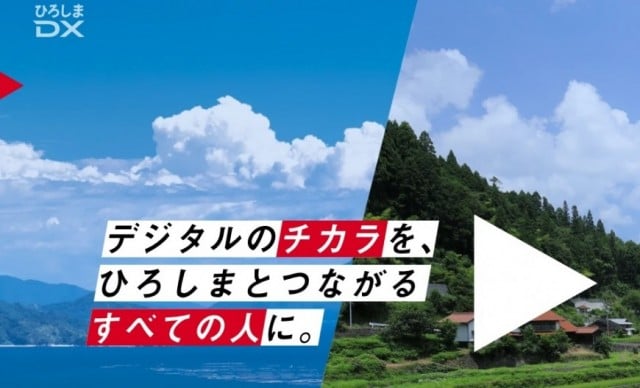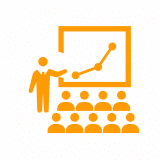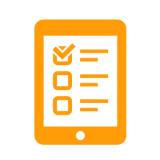新着情報&お知らせ
2024-04-22
注目オススメNEW「DX実践ガイドブック」を公開しました。[広島県DX推進コミュニティ主催]
2024-04-01
【重要】広島県DX推進コミュニティ規約及び個人情報の取扱いを一部改正します。[広島県DX推進コミュニティ主催]
2024-03-27
注目オススメ「DX簡易診断ツール」をリリースしました!~診断時間は約5分!誰でも無料で課題を診断!課題解決の参考となる事例や支援メニューをご紹介します!~[その他DXに関する情報]
2024-03-25
2024-03-25
| RSS(別ウィンドウで開きます) | もっと見る |

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは
広島県ではDXを「広島県を構成するあらゆる主体(企業、教育機関、研究機関、金融機関、県民、行政)が、デジタル技術を活用して、絶えず、それぞれの目指す姿の実現に向けて新たな価値を生み出し続けている状態」と考え、取り組んでいます。

広島県DX推進コミュニティとは
広島県では、県内の企業や事業者、教育機関、行政など、あらゆる主体がDXに対する理解を深め、DXを実践することを促すために、広島県DX推進コミュニティの活動に取り組んでいます。
お問い合わせ
■お問い合わせの際は「個人情報の取扱い」をお読みになり、同意のうえお問い合わせください。